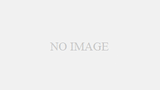リシン仕上げは、モルタル外壁の中でも特に人気の高い仕上げ方法のひとつです。 その繊細なザラザラした質感や落ち着いた艶消しの表情は、和洋どちらの建物にも調和します。 しかし、再塗装の際に正しい施工手順を踏まないと「吸い込みムラ」「塗膜の膨れ」「早期の剥離」といったトラブルが起こりやすいのも事実です。 この記事では、元塗料メーカー営業として多くの現場に立ち会ってきた経験から、メーカー技術資料に基づいた確かなリシン外壁再塗装のポイントを解説します。
1. リシン外壁の構造と再塗装時に起こりやすいトラブル
リシンとは、モルタル下地に骨材(砂や軽量骨材)を混ぜた樹脂を吹き付けた仕上げ材です。 表面には無数の凹凸と微細な空隙があり、通気性は良いものの、塗料を吸い込みやすいという特徴があります。
- 吸い込みムラ: 下塗り不足や劣化したリシン面に塗料が吸い込まれ、ツヤや色にムラが発生。
- 塗膜の膨れ・剥がれ: 洗浄後の乾燥不足で内部に残った水分が蒸発し、塗膜を押し上げる。
- ヘアクラック(細かいひび割れ): 弾性のない塗膜を使用すると、建物の動きに追従できず再発。
これらのトラブルを防ぐには、下地処理と下塗りの選定が重要です。
2. 下塗りの役割:吸い込み止めと密着性の確保が塗装寿命を左右する
リシン仕上げの外壁は、表面に細かな孔が無数にあるため、塗料をそのまま塗ると吸い込まれてしまいます。 その結果、ムラや剥がれの原因になります。 この吸い込みを防ぎ、上塗りの密着性を高めるのが「下塗り材(シーラー・フィラー)」の役割です。
下塗りの主な目的:
- 下地の吸い込みを止め、塗料の発色を均一にする。
- 上塗り塗料の密着力を高める。
- 微細なひび割れを埋め、下地の動きに追従する。
特にリシン外壁では、微弾性フィラーと呼ばれる下塗り材が効果的です。 このフィラーは粘度が高く、下地の凹凸に入り込みながら厚みを形成するため、吸い込みを防ぎ、クラックにも対応します。
3. 洗浄後の乾燥不足が引き起こす「塗膜の膨れ」
外壁塗装では高圧洗浄で汚れやカビを落としますが、その直後に塗装を行うと内部に水分が残ったまま塗膜で密閉されます。 この状態で気温が上昇すると、残った水分が蒸発して塗膜の膨れや剥がれを引き起こします。
乾燥の目安は以下の通りです。
- 夏場:1〜2日程度
- 春・秋:2〜3日程度
- 冬季:3〜4日以上(特に北面や日陰は要注意)
表面が乾いていても内部が湿っているケースがあるため、メーカーでは23℃環境で2〜3日以上(冬季は4日以上)の乾燥期間を推奨しています。
4. ヘアクラック対策:柔軟性のある塗膜で動きに追従させる
モルタル下地やリシン仕上げでは、温度差や地盤の動きによって細かなひび割れ(ヘアクラック)が発生します。 このひびを放置したまま再塗装すると、すぐに同じ場所から再び割れが発生してしまいます。
対策のポイント:
- ヘアクラック部を清掃し、微弾性フィラーや補修パテでしっかり埋める。
- 下塗りで厚みを確保して、塗膜に弾性を持たせる。
- 上塗りには弾性タイプのシリコン塗料やラジカル制御型塗料を選定。
こうすることで、下地の動きに塗膜が追従し、ひび割れの再発を防止できます。
5. 各塗料メーカー推奨仕様と技術資料抜粋
■ 日本ペイント
- 下塗り材: パーフェクトフィラー(水性反応硬化形微弾性フィラー) 使用量:0.20〜0.45kg/㎡(ウールローラー)/乾燥4時間以上(23℃) → 公式製品ページ / 技術資料PDF
- 上塗り材: パーフェクトトップSi(ラジカル制御型シリコン) 耐候性・防藻防カビ性◎ → 公式仕様書
■ 関西ペイント
- 下塗り材: アレスホルダーGⅡ(水性反応硬化形微弾性下地調整材) 希釈率:清水7〜15%(エアレス塗装時) → 製品カタログ
- 上塗り材: アレスダイナミックTOP(高耐候ラジカル制御塗料) 耐候性・防藻防カビ性◎、弾性上塗りとの併用でリシン面に最適。 → 外壁標準仕様書
■ エスケー化研/ロックペイント
- エスケー化研:ミラクシーラーEPO or 弾性フィラー+プレミアムシリコン
- ロックペイント:ハイパーシーラーエポ+ハイパービルロックセラ
各メーカーとも共通しているのは、「リシン・モルタル系下地=微弾性フィラー必須」「乾燥時間の確保」「弾性上塗りの推奨」という点です。 これは実験室のデータだけでなく、現場での長期追跡試験の結果に基づくものです。
6. まとめ:リシン外壁で失敗しないための3つの鉄則
- 吸い込み対策: 微弾性フィラーを厚めに塗り、下地を均一化する。
- 乾燥期間: 洗浄後2〜3日(冬季は4日)以上しっかり乾燥させる。
- クラック補修: フィラー+弾性上塗りで下地の動きに追従させる。
まとめると、
リシン塗装の仕上がりは、上塗りよりも下地処理の出来栄えで決まります。 「どの塗料を使うか」よりも、「どのように下地を整えるか」。 業者選びでは、見積書に使用下塗り材の製品名とメーカー名が明記されているか必ず確認しましょう。